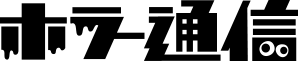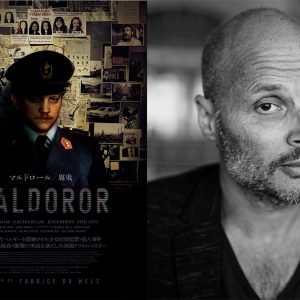この記事は1年以上前に掲載されたものです。

傑作ホラー『フッテージ』のスコット・デリクソン監督×イーサン・ホーク(主演)×ブラムハウス・プロダクションズ(製作)が再びタッグを組んだ注目のホラー映画『ブラック・フォン』が7月1日より公開。デリクソン監督がインタビューに応じてくれた。原作への思い入れや、作品に投影した幼少期の恐怖、トム・サヴィーニが手掛けたマスク、自身のホラー映画のルーツなどについて語ってくれている。
原作は、ジョー・ヒルの短編小説「黒電話」。13歳の気弱な少年フィニーは、連続誘拐事件を起こしている殺人鬼のターゲットとなり、突如拐われて地下室に閉じ込められてしまう。ガランとした地下室には、“断線した黒電話”があった。どこにもつながっていないはずのその電話は、なぜか時折ベルが鳴る。電話口では、その場所で死んだ子供が、少年に何かを伝えようとしている――。

デリクソン監督は、「黒電話」が収録されているジョー・ヒルのデビュー短編集「20世紀の幽霊たち」が発売された2005年当時、書店でそれを手に取り、この物語に惚れ込んだ。この小説について、「連続殺人犯のストーリーとゴーストストーリーの“組み合わせ方”が大好きなんだ」と監督は言う。「これまで誰もやったことがないやり方で、これら2つのことを組み合わせている、という事実を見逃してしまうのはとても簡単だ。しかもジョー・ヒルは、それを閉鎖された環境の中(少年が監禁された地下室)でやってのけている。僕は、それはとても映画的で、新しく、興味深いものだと思ったんだよ」
現実の連続殺人事件とトラウマの克服
デリクソン監督は、長らく心に留めていたこの小説を映画化するにあたり、クリエイティブ・パートナーであるロバート・C・カーギルとともに脚本にも携わった。
「僕は長年このストーリーが大好きで、いつも映画にしたいと考えてきた。でも、それをどう映画化すればいいかわからなかった。なぜなら、ストーリーはとても短いからだ。あまりページ数がないんだよ。それで、70年代後半にデンバーで育った僕自身の子供時代の思い出を組み合わせることを思いついた。僕の周囲にあったバイオレンス(暴力)――僕の家の中の暴力、近所の暴力、どれほど子供たちはいつも喧嘩していたか、どれほどいじめが横行していたか――について考え始めた。そして僕は、これは興味深い環境だ、僕と僕が知っていた子供たち何人かの思い出と「黒電話」のストーリーを組み合わせることが出来る、と思ったんだ。この映画はまさにそういうもの。僕自身の子供時代の思い出と、ジョー・ヒルの短編小説を組み合わせたものなんだよ」

66年生まれのデリクソン監督が子供時代を過ごした70年代のアメリカでは、今なお人々を凍りつかせるような連続殺人事件が多発した。そういった事件は、監督にとって“自分の身にも起こり得るもの”に感じられた。実際に、それはあまりに身近なものだったのだ。
「すべての子供たちがそう感じていた。チャールズ・マンソンの事件が起きたし、テッド・バンディは、僕が住んでいたコロラドに来て、逃げた。とても個人的な出来事もある。僕が9歳の時、隣に住んでいた友達がやって来て、家のドアを叩いた。僕が出ていくと、彼は泣いていた。そして「誰かが僕のママを殺した」と言ったんだ。彼の母親は誘拐され、レイプされて、近くの湖に投げ込まれたんだよ。そして、連続殺人犯の映画がいくつか公開された。『ハロウィン』(78)などだね。初めて、連続殺人犯というアイディアがいたるところにあった。だから、僕の近所のすべての子供たちが、“この目に見えない殺人者の次の犠牲者になるかもしれない”という恐怖の中で、生活することになったんだ」
この映画は、そういった恐怖の感覚を、真に迫る描写で観客に追体験させる。しかし、この物語には大きなカタルシスもある。この映画を作ること自体が、デリクソン監督にとってトラウマを癒やすような効果をもたらしたのだろうか。
「それ(トラウマの克服)は、僕が実際にセラピーを受けてきた結果だと思う。僕は数年、子供時代のトラウマや暴力を扱うのにセラピーを受けてきたんだ。数年それを経験して、僕は“自分が感じたこと”を使って、それをカタルシスとして出せるものを探していた。だから、そうだね。間違いなく、『ブラック・フォン』の多くは、そういうことだよ。僕がセラピーで扱ってきたすべてのことや、思い出などすべてを取って、それをこのストーリーにチャネリングした(注いだ)んだ」
変化する殺人鬼のマスク
原作の連続殺人鬼はスキンヘッドの太った男だったが、本作ではアレンジが加えられた。イーサン・ホークが演じるこの男は“グラバー(The Grabber)”と呼ばれ、原作にはない不気味なマスクをつけている。それは複数の種類が存在し、上下がわかれていて、グラバーはそれを意味ありげに付け替える。その印象的なマスクのデザインは、ホラー映画の伝説的な特殊メイクアーティストであるトム・サヴィーニが手掛けたものだ。
「小説では、彼(連続殺人鬼)はジョン・ウェイン・ゲイシーに基づいているんだ。太ったピエロの殺人犯にね。僕は、少し違うことをやりたかった。あのマスクは、小説の中には出てこない。グラバーが犠牲者たちに自分自身を表現する方法として、さまざまな種類のマスクを使うクリエイティビティを与えたことは、この映画のもっともユニークな側面だと思う」

「僕たちが書いた脚本の中には、2つのマスクしかなかった。それは、笑っている悪魔の絵と、しかめっ面の悪魔の絵が描かれた古いレザーのマスクだった。コメディ/悲劇のマスクのようにね。それから、僕がプリプロダクションをやっている時、映画が完成したら、マスクは、マーケティング部門がこの映画を売るのに使う主なものになることに気づき始めたんだ。そして思った通り、(自分の背景にあるグラバーのマスクの宣伝用の絵をちらっと見て)そういうことになった(笑)。
マスクに関して、何かアイコニックで印象に残るものを作らないといけないのは分かっていた。次のアイディアは、2つのマスクから3つにすることだった。最初は、笑っているのと、しかめっ面のマスクだけだったけど、そこに“何の表情もないマスク”を足すことだった。それから、イーサン・ホークがグラバーを演じることになっていたから、「世界で最大の映画スターの一人がいるんだ。時々、彼の顔を見たくないかな?」とも思った。そしてそのことが僕に、マスクを真ん中で分けるというアイディアをもたらしたんだ」
「なぜなら、彼は“トム・サヴィーニ”だからだよ」

「グラバーはマスクの半分だけをつけることが出来る。(下の半分だけのマスクのときには)彼の目を見ることが出来る。彼の顔は見えないけどね。最後の一つのシーンで、彼はマスクの上の半分をつけていて、下の半分はつけていない。そういったことは僕にとってとても興味深いものになった。この映画を観た人は、“なぜ彼はそれぞれのシーンで、それぞれのマスクをつけているのか”ということをクリエイティブ的に推察するんだ。彼がつけているそれぞれのマスクには理由がある。彼は、自分自身を隠したり、自分をさらけ出して話すために、すべてのマスクをつけている。それがアイディアのすべてだった。僕がデザイナーのトム・サヴィーニに(そのアイディアを)渡したら、彼は完璧なこれらのマスクのスケッチを僕にくれたんだ。それから僕たちは、そのスケッチからマスクを作ったんだよ」
トム・サヴィーニは、監督の求める完璧なマスクのデザインを考え出した。しかし実は、マスクのデザインの依頼をしたのはサヴィーニだけではなかったという。
「はっきり言うと、僕は5つの別々の会社に頼んだんだ。彼らみんなに同じ指示を与えた。「3つのマスクで、一つは笑っているもの、一つはしかめっ面のもの、そして一つは口がまったくないもの。そして、それらすべてを上下2つに分けて欲しい。マスクの上半分だけや、下半分だけをつけられるように」とね。それからもう一つの情報を渡した。それは、昔の白黒映画『笑ふ男』のイメージだった。依頼をしてから4日か5日後に、トムが僕にデザインをくれた時、他のみんなとは違うレベルのものだったんだ。なぜなら、彼は“トム・サヴィーニ”だからだよ。それを見た途端、僕は「おお、これだ」と言ったよ(笑)。だから僕は、彼が伝説の人だから選んだわけじゃない。これ以上ないほどとても怖いマスクの絵を描ける若くてハングリーな人たちがいる4つの会社を今でも負かすことが出来るから、彼は伝説の人なんだよ」
“グラバー”を高次元で表現したイーサン・ホーク

そうして出来たマスクを身に着け、グラバーを演じたイーサン・ホークの演技にも目を奪われる。マスクでは隠しきれないほどの邪悪さをまとい、言葉を発するだけで見る者を硬直させ、被害者が強烈に畏怖を感じるグラバーという存在を体現してみせた。その演技は、彼とデリクソンとで話し合って出来たものではなく、ほとんどイーサン・ホークが自分自身で見つけ出した答えだったようだ。
「正直に言って、(グラバーの演じ方について)そんなに話さなかった。セリフはとても独特だし、すごくいいと思う。でも彼は、あのキャラクターについて高い次元の理解を現場に持ち込んだ。彼がそうするだろうというのはわかっていた。それがイーサンなんだ。そして彼がやることは、とても奇妙で、とてもユニークで、それがどこからくるのかいつも理解できなかった。でも、それが僕を動揺させ、心を掻き乱されるものであることは知っていた。だから、彼に説明しようとして時間を使うよりも、僕はただ彼に好きにやってもらった。僕の指示のほとんどは、「もっと早く、イーサン」とか「もっとゆっくり、イーサン」とかいうものだった。「もう少し声を大きくする必要があるよ、イーサン」とかね(笑)。そういったことだったよ。世界で一流の役者たちと仕事をするとき、多くの場合、良い監督になるには彼らの邪魔をしないことだと思う」
地下室のデザインの裏側
本作においてメインの舞台となるのが“地下室”だ。そこは監禁された子供の孤独感や閉塞感が投影された場所であり、観客にとっても“息の詰まる場所”になってしまう可能性があった。「観客が地下室に行くのが嫌にならないようにする方法を見つけないといけなかった」と監督は言う。

「僕にとって、単調にならないように撮影出来る部屋をデザインするのは重要だった。同じ空間にいることが退屈にならないようにする方法を見つけないといけない。それで、さまざまな方法で撮影できると感じたサイズを選んだんだ。ワイドレンズを使えば、とても大きく感じられるし、もっとタイトなレンズを使えば、とても閉所恐怖症みたいに感じさせられる。
また、天井が上がったり下がったり出来るように作ったんだ。いくつかのシーンでは、もっと大きく感じさせたかったから、もっと天井を高くした。もっと狭く感じられるようにしたい時には、天井を下げて、もっと閉じ込められた感じにした。天井の高さが変わったとは、決して気づかないよ。誰もそれに気づかない。そして色だけどね、僕は錆びた線のところで分けたかったんだ。プロダクション・デザイナーに、その部屋全体に、ギザギザの裂け目があるようにして欲しいと言ったのを覚えている。それはフレームを分けることになる。だから、僕はいつもフィニー(主人公)を壁に向かって撮影していて、壁に裂け目の水平線があることは、それをどうフレームすればいいか僕にチョイスを与えてくれるんだ。それがとても助けになった。その線を外してフレームするか、高いところでフレームするか、低いところでフレームするか、というふうにね。それが、いくつかビジュアルの可能性を与えてくれたんだ。
僕はこの地下室を、恐ろしくて危険だけれど、違う見方をしたときに、絵画的である意味美しく見えるようにもしたかった。それは僕にとって、映画が進むにつれて変わっていくミステリアスな空間のように感じられる。それはすべて意図的なものなんだ。すべては、その空間を退屈なものにしないようにする僕の戦略の一部だったんだ」
デリクソン監督のホラー映画愛

『ヘルレイザー ゲート・オブ・インフェルノ』(00)に始まり、法廷物ではあるが悪魔祓いを題材にした『エミリー・ローズ』(05)、『フッテージ』(12)、『NY心霊捜査官』(14)など、ホラーに関連する映画を多数手掛けてきたデリクソン監督。MCU作品『ドクター・ストレンジ』(16)の監督としても高く評価されたが、再びホラージャンルに舞い戻ってきた。そんな彼のホラー映画の原体験と、ホラー映画を撮るようになった経緯を伺ってみた。
「僕の両親はホラー映画のファンじゃなかったから、僕は子供の頃ホラー映画を見なかった。僕が観たのを覚えている初めてのホラー映画の一つは、『ティングラー/背すじに潜む恐怖』(59/ウィリアム・キャッスル監督作)だった。白黒映画だけど、映画のど真ん中に、血が蛇口から出てきて、浴槽が真っ赤になるシーンがあるんだ。とても怖いんだよ。それには本当に動揺させられたことを覚えている。それから、僕が子供の頃見てとても怖かったのは、テレビで見たR指定の予告編だった。『エクソシスト』の予告編にはものすごく怖がらせられたよ。ベッドの支柱が床に叩きつけられていて、僕ぐらいの年の女の子が叫んでるんだ。『オーメン』の予告編も怖かった。これらR指定のホラー映画は、すべて素晴らしいクラシックなホラー映画だけど、子供の頃は本当に怖かったんだ。
それから僕は、テレビで初めて放映された70年代のホラー映画を見始めた。『ヘルハウス』(73)も観たよ。間違ってなければ、リチャード・マシスンの小説を基にしていたと思う。とても怖かったけど、でも大好きだった。素晴らしかった。あの映画のことを今でもとてもよく覚えているよ。マシスンの小説は、何年も後になって読んだ。素晴らしい小説だ。高校に入ったころには、『ハロウィン』(78)の映画を見始めた。友達を呼んで、『ファンタズム』(79)や、あの時代のすべての素晴らしい伝説の映画を見たんだ。素晴らしい体験だったよ」
『サスペリア』と日本のホラー映画の影響
「僕に“ホラー映画のフィルムメーカーになりたい”というインスピレーションを与えてくれた映画は、ダリオ・アルジェントの『サスペリア』だった。僕は当時フィルムスクールにいて、怖い題材を扱うコツがあることが分かっていた。サスペンスをどのように作り出せばいいか知っていたと思う。でも、必ずしもホラーの監督になろうと思っていたわけじゃない。でも『サスペリア』を観たとき、ホラー映画に対する感じ方が大きく変わった。なぜなら僕はインターナショナルなホラー映画を観たことがなかったからだ。これは、Jホラーがアメリカでウケるようになる前のことだった。初めて『サスペリア』を見て、「オーマイゴッド。ホラーでハイアート(優れた芸術)を作れるんだ」と気づいたんだ。あれはスラッシャー映画だった。でも明らかに、ハイアートであろうとしていた。とても野心的で、シリアスな映画にしようとしていたんだ。そしてそのことが、僕をもっと芸術的なクラシックのホラー映画を見ることに向かわせた。『ローズマリーの赤ちゃん』、もちろん『エクソシスト』、『オーメン』、『シャイニング』といった、偉大な監督たちが1回だけ作った(ホラー)映画をね。
でもその後直ぐ、90年代初頭に、日本のホラー映画がヒットし始めた。それが、僕にとっては本当に(ホラー映画を作ろうという)気持ちにさせるものだったと思う。僕は、このホラー・ジャンルには成長する余地がたくさんあると気付いたんだ。とても興味深いことが起きていたんだよ。そして今は、フィルムメーカーたちが、一般的な観客たちとつながるハイアートのホラー映画を作っている興味深い時代の一つだと感じる。たとえば『ウィッチ』や『ヘレディタリー/継承』、『イット・フォローズ』のように。これらは、すごく怖いアート映画で、観客はそれらに反応しているんだ。それは素晴らしいと思うよ」
映画『ブラック・フォン』
7月1日(金)全国公開
製作:ジェイソン・ブラム(ブラムハウス・プロダクションズ)
監督:スコット・デリクソン(『ドクター・ストレンジ』、『フッテージ』、『エミリー・ローズ』)
原作:ジョー・ヒル「黒電話」
出演:イーサン・ホーク、メイソン・テムズ、マデリーン・マックグロウ
配給:東宝東和
上映時間:1時間47分

(C) 2021 UNIVERSAL STUDIOS. All Rights Reserved.