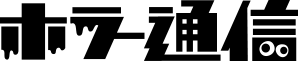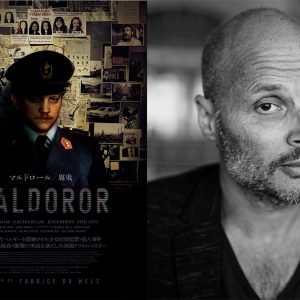この記事は1年以上前に掲載されたものです。

現在、池袋シネマ・ロサで3週間限定公開中の映画『みぽりん』。ホラー・コメディの形をとりアイドル業界の暗部へ斬り込んだ本作は、2019年春に神戸の元町映画館で流された予告編で火がつき、公開前から「みぽらー」と呼ばれるファンを生んだ異色の作品。同年の「カナザワ映画祭」で観客賞を受賞し、その後、元町映画館で上映が始まると1週間の上映期間全てで満席を記録する。初のシネコン上映となったOSシネマズ神戸ハーバーランドも満席完売。
その実績を引っ提げて東京へ乗り込んだ松本大樹監督に、“みぽりん”役の垣尾麻美さん、“アイドルおたくカトパン”役の近藤知史さん、“アイドル事務所マネジャー”役の合田温子さんを交え、『みぽりん』にかける思い、インディーズ映画へのこだわりを伺った。
<あらすじ>
声優地下アイドルユニット「Oh!それミーオ!」でセンターを務める神田優花。ソロデビューが決まったものの、実は音痴である優花の歌声にプロデューサーの秋山とマネジャーの相川は頭を抱えていた。グループメンバー里奈の紹介で、優花はボイストレーナー「みほ」の指導を受けることとなり、人知れず六甲山にあるみほの山荘へ向かう。優しくもどこか異常性を垣間見せるみほに戸惑う優花。レッスンを進めていくなかで二人の関係には徐々に亀裂が入り、「監禁」という事態へと発展していく。ライブ前日になっても連絡のつかない優花を心配した秋山と相川は、優花推しファンの“カトパン”こと加藤の指摘でようやく事態に気がつき、3人は優花を助けに六甲山へと向かうのだが…
「無名の人たちがたった一本の映画で起こした“社会現象”が大変な衝撃だった」

――『みぽりん』はどのようにして生まれたのでしょうか。
松本大樹監督(以下、松本):子どものころから映画は大好きでした。就職を考えるときになって、いつか映画を撮るんだという漠然とした思いで映像関係の職を選びました。編集スタジオでのオペレーターに始まり、やはり実際に撮影をしてみたくなって企業コマーシャルやミュージックビデオを撮り、根本からつくってみたくなって制作会社へ…というと聞こえはいいんですが、僕は本当にダメ人間で、会社勤め自体が合わなかったんです。同じところに毎日通うということができなくて、もって1年そこそこ、3年続かない。飽きちゃうんですね。飲み会みたいな会社文化も好きじゃなくて、なじめませんでした。それでも映画をつくりたいという気持ちは強くあって、ただ、関西で今、映画の仕事にかかわれる機会ってほとんどないんですよ。ましてや自分が監督として映画を作るだなんて夢のまた夢だと悶々としていたところに、去年の夏です。上田慎一郎監督の『カメラを止めるな!』の関西上映が始まり、TOHOシネマズ梅田の一番大きなスクリーン(747+4席)が満席になったんですね。東京での上映の熱狂的な様子は噂には聞いていましたが、正直、上田監督のこともキャストの方々のこともまったく知りませんでした。そんな無名の人たちがたった一本の映画で起こした“社会現象”を目の当たりにして、大変な衝撃を受けました。同時に、関西にいるから仕方がないと変なコンプレックスを抱えて踏み切れないでいた自分が情けなくなり、もう言い訳はできないぞと強烈に背中を押された思いがしたんですね。
そこから脚本に取り掛かったのが8月。2カ月で一気に書き上げました。テーマと撮影地は決めていたんです。六甲山を舞台にしたホラー映画。六甲山って、昔から都市伝説みたいなものがあるんですよ。戦(いくさ)で負けた武将6人の首が甲(かぶと)と共に埋められているから「六甲山」というんだとか、「牛おんな」が出るだとか。脚本を練り上げる過程で、ヒントを求めて昔のホラーやサスペンス作品を観なおしていました。最近の映画はCGや特殊効果がすごいですよね。そこにお金はつぎ込めないし、逆に2、30年前の作品なのに今も愛されている映画って、必ず何か理由があると思ったからです。何が人を惹きつけるのか、何が人を怖がらせるのかと考えながら観ていった中の一本が『ミザリー』でした。登場人物が4人しかいないのに、最後まで緊張感で引っ張る演出がうまいんですね。これだ!と思いました。登場人物を極力絞って、場所も山荘というほぼ1カ所固定にする。それなら今の自分でも作れるんじゃないか。今回「みぽりん先生」を演じた垣尾麻美さんとは、一度、映像の仕事をご一緒したことがあって、いつか垣尾さんで何か撮ってみたいという気持ちもありましたから、それなら垣尾さん主演の日本版『ミザリー』にしようと決めました。
もう一つ、背中を押す出来事があって、実はクランクインの前日に離婚したんです。実際に映画を作ってみて痛感していますが、何が楽しくてこんなことをやっているんだというぐらいにお金にならない。自分の場合は、家族がいたら踏み切れていたかどうか疑問です。もう何も失うものがないし、守るものもない。崖っぷちに立たたされるという環境に動かされた面もあるかもしれません。
「期限は10日間。人を巻き込む以上、自己満足では終わらせられない」

――物語の要になる山荘ですが、ピンポイントに六甲山で探すのにはご苦労があったのではないですか。
松本:めちゃくちゃ大変でした。こんな素人が、それもホラー映画を作りますだなんて言って協力をあおいだところで怪しさしかなくて、頼む端から断られました。そのころちょうどTwitterを始めて、「六甲山で山荘を持っている方、貸してください」とつぶやいたら、反応してくださった方があって、快く貸し出してくださることになったんです。その方がちょっと変わった方で、ご自宅で鳥を100羽以上飼っておられるんですが、山荘は、そこから厳選した精鋭たちを代わる代わる連れていっては放し飼いにして遊ばせる場所だったんですよ。劇中に出てくるの鳥の置物などはその方の私物です。雰囲気がよかったのでそのまま使わせていただきました。実はその方、職業が看護師なんですよね。まさに『ミザリー』のアニー。一人でご挨拶に伺ったときは、このまま監禁されるんじゃないか…という妄想が働いてしまいました(笑)。実際はとても優しい方で、撮影が終わったあとスタッフ、キャスト一同をバーベキューに呼んでくれたり、神戸での上映中もずっと応援してくださったり。今もいい関係が続いています。いつかその山荘を含むロケ地ツアーをしてみたいと思っています。
撮影自体は、週1ペースで3カ月にわたって行い、実質10日間で撮り上げました。助監督も美術もいませんから、一人が何役もこなす大変な現場でした。それでも最初から追撮はせずに10日で撮りきるというルールを自分の中に設けていたんです。理由は二つあって、僕は園子温監督が大好きなんですが、園監督は『冷たい熱帯魚』を10日間で撮影したと聞き、あれほどの作品をたった10日間で撮れるのか。それなら自分も挑戦してみようと思ったのが一つ。もう一つは、自主映画にありがちだと思うんですが、広げるだけ広げて作品が完成しないという事態だけは、絶対に避けたかったんですね。人を巻き込む以上は、結局作品はできなかったけれども自分は納得している、満足だ、みたいなことにはしたくなかった。だから、10日間きっちりスケジュールを組んで、ここにかけられる予算はこれだけ、それ以上はやらないしできない、撮れたものを使う。ほとんどすべての場面を一発で決めました。そういうふうにしないと、いつまでたっても終わらない、完成しない気がしたんです。

――『ミザリー』の世界に地下アイドルの話を持ち込むという発想はどこから生まれたのでしょうか。
松本:脚本は、吉永君というスタッフと相談しながら書いていったんですが、日本版『ミザリー』を作るといっても、まったく同じようにやってしまったらただのリメイクですよね。設定を日本に置き換えたときに、何か独自の味を出せないかと考えて、アイドルはどうだろうねという話になりました。僕自身、アイドルのミュージックビデオや『がっこうぐらし!』に出演していたアイドルのインタビューを撮影したことがあって、彼女たちから“アイドル光と影”の両面を何となく聞いていたんですね。当時はちょうど、特に地下アイドルの悲惨な実態が明るみになり、社会に拡散されていたころでもありました。そんな中で起きた農業アイドル「愛の葉(えのは)Girls」の子が自殺してしまうという事件が決定打となりました。アイドルの世界で起こっていることを風刺として入れてみることにしたんです。その要素は、映画の冒頭や、みぽりん先生が契約書に半ば強引にサインさせたり、会話の中から「給料をもらっていないばかりか、レッスン代を事務所に払っている」といった事実が浮かび上がるという形で入れています。ただ、映画をごらんになった方からは、「みぽりん先生は真面目な常識人。(主人公の地下アイドル)ユカちゃんのほうがモンスターだ」という声もあって、なるほどなと思いました。僕は今、36歳なんですが、みぽりん先生とユカちゃん、どちらの気持ちもぎりぎりわかるんですね。両世代の感覚をうまくくみ取れたと思っています。観る人によって、どちらに感情移入してしまうのか、分かれるのかもしれません。そういう楽しみ方もしてもらいたいです。
「役者の持つ一番いい部分を最高の形に料理するのが監督の仕事」

――癖がありつつも、実際にいそうなキャラクターというのは、どのように作り上げていかれたのですか。
松本:キャラクターは、役者さん自身の性格を想像しながら作っていきました。何がこの人の魅力なのか、その魅力を生かすにはどうしたらいいかを考えて、ブラッシュアップしていった形です。役者さんには打ち合わせのときに何度か即興劇をやってもらい、そのときのリアクションをそのままキャラクターに反映させている部分もあります。極端な話、演技が下手な人でも、絶対にいいところがあると思うんですよ。その“下手さ”が生きるようにすればいい。その人が持つ一番いいところを最高の形に料理するのが監督である僕の仕事だと『みぽりん』であらためて思いました。だから、役者さんに合わせて設定も変えていきました。例えば、「カトパン」を演じた近藤君は、当初はマネジャー役予定でしたが、「アイドルおたく」でいけるかもとひらめいて、配置換えをしたんです。近藤君はそこからいろいろと研究して「実はアイドルおたくでしょ」と誰もが認める「プロおたく」として役づくりをしてきてくれたので、すごいなと感心しました。
――「某(なにがし)」という謎の役はどのようにして生まれたのですか。
松本:そうして、それぞれの役者さんをはめ込んでいったときに、6人が6人とも魅力的でいい感じにまとまってしまったんですね。もう一つスパイスを入れなければ、うまく流れ過ぎてしまう。そこで流れきらない何か引っかかりが欲しいと思いました。それが「某」です。演じたのはヘアメイク担当の怜さんという方ですが、実は明確な設定はありません。僕は、彼女にしか出せない凜としたたたずまいや美しさが画面のどこかに存在するだけで、ほかの役者さんに出せない何かを映画に付け加えてくれると感じたんです。思いきって話を振ってみたら、まんざら嫌でもなさそうだなとつけいる隙を感じて、これはワンチャンスあるぞと押しまくって「某」が誕生しました(笑)。
――役者の皆さんにお伺いします。キャラクターは皆さん自身の投影だということですが、実際に演じてみてどうでしたか。
垣尾麻美(以下、垣尾):みぽりんが怒る場面で、普通に説教をする感じでやったら「全然怖くない、迫力がない」と言われてしまったんです。配役の露木さんから「全感情で笑ったり泣いたりしたらいいんじゃないか」とアドバイスをいただいて、ハイテンションで笑ったあとに怒るという演技をしてみたら、それでいきましょうということになりました。そのワンシーンだけかと思ったら、ほかのシーンでも笑ってくださいと言われ続け、途中から笑いのレパートリーがなくなってきてしまって。もっといろんな笑いを見せられたらよかったなというのが今も反省点としてあります。『ミザリー』のキャシー・ベイツってすごくかわいいところがあるんですよね。怒りのボルテージが上がりきったところはものすごく怖いんですが、ただ怖いだけじゃない、いじらしいところもあるんです。みぽりんも同じで、ただのテンションが変な怖い人ではなく、愛されたい哀しさも表現したいと思って演じました。

近藤知史(以下、近藤):僕はアイドルファンではないんですが、アニメや漫画が好きで、自分の中には確実におたく気質はあると思っています。覚えていないんですが、3歳ぐらいのとき鉄道に夢中になって、子ども向けの本では飽き足らず、大人のマニアが読む鉄道模型雑誌を買ってもらっていたみたいです。そのマニア気質のベクトルをアイドルおたくのほうに向けた結果が「カトパン」です。「本物みたい」と言っていただけるサイリウムダンスも、監督から突然「来週オタ芸のシーンを撮るのでよろしく」と言われて、1週間でYouTubeに上がっているサイリウムダンスを見まくり、講座的な動画で自主練習をして仕上げたんですよ。実際にサイリウムダンスをしている友達にどれが一番見栄えのいいダンスかを聞いたところ、「サビで踊る『ロマンス』が一番映える、大きく見えるよ」と言われ、僕は運動神経がなくてダンスも苦手なんですが、その「ロマンス」だけは必死にマスターしました。どこまで撮影するかわからないので、Aメロ、Bメロもひととおり踊れるように「ロザリオ」とか「サンダースネイク」も練習して備えました。サイリウムダンスを踊っている方って動きのキレが半端ないんです。アイドルファンの方に、こいつにわかだとか、練習足りてないとか思われてしまうんじゃないかと不安でした。だから、映画をごらんになったアイドルファンの方から「カトパンの言動はすごくリアリティあったよ。ダンスもよかった」と褒めていただいたときにはうれしかったですね。監督からは一つだけ注文があって、「ドラマに出てくるようなステレオタイプなおたくにはしないで。シャツインしたり、バンダナとか、そういうのはやめて」と言われました。僕が演じたのはいたって普通の人、でも、おたくなんですよ。実際のアイドルおたくの方ってそういう方が多いんじゃないかなと思います。
合田温子(以下、合田):私には何も指示がありませんでした。みぽりん先生は急にキレ出すとか、ユカちゃんはのほほんとしていて、リナちゃんもカトパンもみんな濃いという面子の中で、私は、緩衝材じゃないけど、一人ぐらい普通のポジションの人がいないと映画がうるさくなると思って、あまり目立たないように演じていました。ある方が「あなたみたいなポジションが一番難しい。際立ってもいけないし、影が薄すぎてキャラクターとして成り立たなくてもダメ。そのバランスがうまくとれていた」と言ってくださったんですね。そのとおりできていたかは別にして、役柄の解釈としては間違っていなかったんだなと安心しました。
「最後の10分はマスターショットなし。あの場の熱量をそのまま伝えたかった」

――劇中のアイドルソングも含めて、音楽にはかなり凝っていますね。
松本:神戸はジャズの街。だから、オープニングにはエラ・フィッツジェラルドの歌をもってきました。彼女って20世紀を代表するトップ・ジャズ・ボーカリストだし、“完璧なロマンスの世界”を歌っているんですが、その人生は波瀾万丈だったんですよね。二度の離婚を経験し、糖尿病で目が見えなくなり、両足を切断して、最後は薬に溺れて死んじゃった。みぽりん先生は似ているところがあるんですよ。エンディングで流れるクラシックはベートーヴェン「第九交響曲」の第四楽章です。第四楽章って、第三楽章の否定から入るんですよね。「そうじゃない、純粋に歌うことを楽しみましょう」という歌詞。『みぽりん』も『ミザリー』をたどってきたけれども、「そうじゃない、純粋に映画を作ることを楽しみましょう」という思いを込めました。もう一つ、「第九」では「神様が現れたことを喜ぼう」という物語が歌われています。アイドルの語源ってラテン語の「偶像崇拝」から来ているんですよね。もともとは神や仏といった存在を像の形に模して崇拝するという意味なんです。その「神」たるアイドルが現れたことを喜ぼうという含みもあります。
――カメラワークにもこだわりを感じました。
松本:撮り方もかなり『ミザリー』を参考にしています。キャシー・ベイツはすごく小柄な女性ですが、怒りのスイッチが入った瞬間、20mmぐらいの広角レンズを使って、接写して撮ってあの迫力になっているんです。そのやり方がうまいなと思って、みぽりん先生にも同じ方法で迫りました。ただし、垣尾さんはキャシー・ベイツより小柄なので、もっと魚眼の、12mmレンズを使っています。それで生まれたのがあの映像です。シャッターを落とした撮り方は、クリストファー・ドイルのまねです。ちゃっかり好きなものを入れてしまいました。
もうちょっと引きの画があったらいいねと言われることもあるんですが、僕の中にとにかく接写したい欲があったんです。最初はきれいに撮ろうとしていたんですが、途中から違うなと思いました。画がきれいとかどうでもいい。役者さんがいい芝居をしていたら、どこから撮ってもいいシーンになることに気がついたんですね。最後の10分は、マスターショットがありません。何が起きているかわからない撮り方をしています。あの場の熱量をそのまま伝えたい。そのためには、近くで撮ったほうが伝わると思ったというのもあります。
――その「ラスト10分」ですが、「映画が壊れる」という宣伝文句どおり、まさに壊れましたね。
松本:よく映画への冒涜だと怒られます。映画は芸術だとか、映画は愛だとか言う人もいますが、僕は、何より役者さんの芝居と音楽と映像と全てが組み合わさったときに生まれるもの、それをぶっ壊しながらも、最後はすべてを圧倒する形で終わりたかったんです。実際、絶叫上映でも、ラスト10分はどんどん盛り上がっていきますが、あの場面のところにさしかかると、急に静かになるんです。そういうふうに人を圧倒する力が映像にはあると思っています。ただ一方で、僕は自分の中に冷めている部分もあって、しょせん映画でしょ、作りものでしょという感情もあります。客観性があったから、積み上げてきたものをある意味で台無しにするということができたのかもしれません。マネジャー役の合田さんが「バランスを取る役だと思って演じた」とおっしゃいましたが、確かにそうなんです。彼女がいなければ物語は進んでいかなかったんですが、そんな彼女も無事では終わらせたくなくて、それであんなふうになりました。それぞれのキャラクターに必ず一つ、見せ場を用意したかったんですね。『みぽりん』には僕の大好きな『ザ・フライ』のある場面を模して取り入れていますが、あんなに好きな映画なのに、話をあまり覚えていないんですよね。ただ、不思議とその一場面だけが強烈に記憶に刻まれている。『みぽりん』だって1年後には誰も話を覚えていないかもしれません。それでも、あの場面だけは覚えている、あれって何だったのかなと残る作品にしたいという思いが強くありました。
『ミザリー』のアニーって、最後がかわいそうなんですよ。観た方の感想も「ああいうサイコパスっているよね」というものが多くて、そんな終わり方は嫌だなと思いました。みぽりん先生をただのサイコパスで終わらせたくなかったんですよね。『危険な情事』という作品にはラストが二つあって、劇場公開されていないバージョンが僕は大好きなんです。格好いいエンディングだなと思いました。みぽりん先生にはその格好よさを受け継いでほしいという願いを込めてのあのラストです。実は、ちゃんとしたエンディングも用意していたんですよ。みぽりん先生があの場にいる全員を殺して終わり。でも、それでは予想の範囲を超えない、ごく普通の終わり方じゃないですか。吉永君には「念のためそのバージョンも撮っておこう。DVDにするときに、Wエンディングで好きなほうを選べますという形にもできるし」と言われましたが、逃げ道を残してはいけないという強い気持ちで、エンディングはあのバージョン一本勝負です。
「『ジャパニーズ・ロッキー・ホラー・ショーだ』劇場との一体感で生まれた“人力4DX”」

――「人力4DX」という上映スタイルが話題になっていますが、どのようにして生まれたのでしょうか。
合田:元町映画館での上映が決まったとき、映画館のほうから、最終日は応援上映にしませんかというご提案をいただきました。上映は1週間しかないのに、お客さんだけで盛り上がれるのかなと心配になって、出演者でフォローすることにしたんですね。最初は上映前に応援上映の注意点、声出しポイントの解説をする程度だったんですが、あるとき、スクリーンの横で垣尾さんがみぽりん先生の台詞に合わせて叫んだのがお客さんに大好評だったんです。
近藤:それを受けてカトパンも画面に合わせてサイリウムダンスをしたり、出演者がそれぞれ自分で考えて何かするようになったんですね。そのうち、映画への突っ込みをスクリーンに向かってではなく、その場にいる役者に投げかけてくるお客さんが出てきて、僕らもそれに対してレスポンスを返すということを繰り返していくなかで、そこにハマる人が出てきたんですよ。
松本:応援上映で有名な塚口サンサン劇場では、オープニングから観客の皆さんの叫ぶ声が大きくて映画の音声がかき消されてしまうという事態が起こりました。劇場のスタッフに音量を上げてくれるように頼んだところ、「このままのテンションは続かないでしょう」。ところが、テンションは下がるどころか上がる一方で、慌てて音量を上げてもらいました。最初に練習したときには、こうなることはまったく意図していませんでした。劇場との一体感で生まれてきたのが「人力4DX」です。「ジャパニーズ・ロッキー・ホラー・ショーだ」なんていうお言葉をいただいたり、応援上映しか来ないというか、関西から東京の応援上映に駆けつけてくれる方もいます。だからこそ、ゼロか100か、評価が極端に分かれる映画なんだと思っています。神戸新聞の記者の方からは、「クソ映画だと思っていたけれども、絶叫上映を観たら恐れ入りましたという気持ちになった。こういう映画だったのか」という感想をいただきました。池袋シネマ・ロサでも「人力4DX上映」を期間中合計3回行います。12月24日と30日、1月4日です。詳しくは『みぽりん』公式サイトか、シネマ・ロサさんのサイトでご確認ください。
――もともとカナザワ映画祭で観客賞をとり、神戸での上映となったわけですが、そこまでの盛り上がりをみせたのはなぜでしょうか。
松本:元町映画館での上映に際しては徹底してチラシ配りをしました。受け取ったが最後、劇場に拉致して監禁してやる!というぐらいの気持ちで配っていましたね。その日の上映時間ギリギリまで映画館の前に立って、通る人たちに片端から渡していきました。9月から11月まで続けて、10万枚刷ったチラシがほとんどなくなりました。100人に1人ぐらいは来てくれた計算でしょうか。帰りがけのサラリーマンがそのまま寄ってくれたこともありました。
チラシのデザインには賛否両論あります。実際、「気持ちが悪い」と受け取ってくれない人もいました。カフェに置いたら「お客さんからクレームが来た」と言われたこともあったし、別バージョンを作ってくれということで、一応用意もしました。でも、僕は絶対にこれでいきたかったし、宣伝自体初めてだから、加減がわからなかったんですよね。配ってみて、ああ、これはダメなんだなと初めてわかったというか。今だったら別のビジュアルにしたかもしれません。最初だから怖いもの知らず。お客さんの反応が読めないなかで作ったのが、逆によかったかもしれません。
「次も絶対に自主制作。インディーズでどこまでできるか、チャレンジしたい」
――1作目はある意味、変化球の作品でした。今後の展開、次回作についての構想はありますか。
松本:『みぽりん』は初上映以来ずっと一館一館の上映を大事にしてきました。イベントを開き、そのおかげで盛り上がったけれども、経済的にはまったく成り立っていないんです。今回の東京遠征にもお金がかかりましたし、僕は今、制作で生じた借金を抱えている状況です。そのことは神戸の週刊誌にも書かれてしまいました。このスタイルを続けていくのには無理があるので、関西での盛り上がりを受けて東京でも話題となり、各地から「うちでも上映したい」という手が挙がってくれるのが理想の展開です。東京での3週間の状況を見て今後を決めたいと思っています。配信という手もありますが、まずは劇場で観てほしいですね。
今回の東京遠征に出演者全員を連れてきたのは、この作品をステップにチャンスをつかんでもらいたいという気持ちがありました。何度も言うように、関西では映画に出演する機会を得ることは難しい。だからこそ、僕みたいな新人の自主制作映画への出演を快諾してくれ、労をいとわず全面的に協力してくれたのでしょうから。僕なりの感謝の気持ちをあらわしたいと思いました。カトパン役の近藤さんは、次回作が決まって撮影も終わり、間もなく公開されると聞いています。
近藤:神戸のお寺の住職で“破戒僧”といわれた故・平井尊士さんを描いた『真言アイロニー』という作品です。海外映画祭への出品は決まっていますが、国内上映は今のところ1月18日(土)の完成披露試写会のみです。
松本:次にやりたい企画はたくさんあります。まずは『みぽりん』でつくった借金を返して、それが2年後、3年後になろうとも、次も絶対に自主制作で撮ります。神戸に根づいた作品を、自分の表現を守りながら作っていきたい。東京に出てきて商業映画を撮りたいとか、監督として売り出したいとか、配給についてもらいたいという気持ちには一切ないんですよ。お金を出してもらう代わりにあれこれと口を出されるぐらいなら、借金してでも自分の作りたいものだけを作りたいです。そのためには、何とかしてお金を回すサイクルをつくらなければならないと考えています。インディーズでどこまでできるか、チャレンジしたいんです。同時に、映画にかかわりたい人が映画で食べていける状況をつくりたいとも思っています。関西の現場には、造形、小道具、何をやるにしてもプロが足りないんです。映画を作り続けることによって人を育てたいです。松本組じゃないですけど、そんなふうにスタッフを組んで、安定して作品を作り続けていけるようにしたいです。
[聞き手・文:TOMOMEKEN]
『みぽりん』
12月21日(土)池袋シネマ・ロサで3週間限定公開中(1月10日(金)まで)
1月10日(金)より川崎チネチッタにて上映決定
監督・脚本・撮影:松本大樹
CAST/役
垣尾麻美/みほ(ボイストレーナー役)
津田晴香/神田優花(アイドル)役
井上裕樹/秋山快(プロデューサー)役
mayu/木下里奈(アイドル)役
合田温子/相川梢(マネージャー)役
近藤知史/加藤淳(アイドルファン)役
企画・製作・配給:合同会社CROCO
2019/108min/日本/16:9/ステレオ
作品公式サイト:https://crocofilm-miporin.com/
池袋シネマ・ロサ:http://www.cinemarosa.net/
(C)CROCO