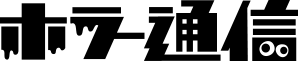この記事は1年以上前に掲載されたものです。

特撮番組を彷彿とさせる“子供向け”要素と、スプラッターをかけ合わせた異色のSFスプラッター『サイコ・ゴアマン』が7月30日より公開される。
本作は、破壊と殺戮を繰り返してきた“残虐宇宙人”が、ひょんなことから8歳の少女に絶対服従せざるを得なくなるというストーリー。残虐宇宙人は“サイコ・ゴアマン(PG)”と名付けられ、生意気な少女ミミとその兄ルークの子供らしい遊びに延々付き合わされる羽目になる。ユニークなストーリーもさることながら、おもちゃ売り場からかき集められてきたような、個性的な“怪人”がたっぷり登場するのも見どころだ。
本作を手掛けたのは、『マンボーグ』や『ザ・ヴォイド 変異世界』を監督したスティーブン・コスタンスキ。カナダの過激映像集団「アストロン6」に所属し、オリジナル作品を作る一方で、特殊造形のアーティストとして様々な大作映画にも携わってきた経歴を持つ。本作では、ミミの父役を「アストロン6」のアダム・ブルックスが演じ、その他のメンバーも特殊メイクをして怪人役で出演している。
このたびZOOMインタビューに応じてくれたコスタンスキ監督に、本作のキャラクター作りや、ファンには嬉しい“あのキャラ”の登場、ホラージャンルへの想いなどを伺った。

[画像:ZOOMインタビューに応じるコスタンスキ監督]
――子供のころに思い描いていたことが本作のアイデアの根源になっているそうですが、それについて詳しく教えていただけますか。
コスタンスキ監督:子供のころ、土曜の朝にやっている子供向けのアニメに夢中だったんです。「トランスフォーマー」や「マスターズ・オブ・ザ・ユニバース」が大好きだった。『スター・ウォーズ』の大ファンでもありました。僕が特に好きだったのは悪役だったんですね。メガトロンやスケルター、ダースベイダーとかですね。「自分がその一味になれたらどうしよう?」「もしスケルターの仲間になれたら、彼にどんなことをやってもらおうかな」みたいなことを考えていた。そういうイメージが、今回の作品につながっているんです。
――自分を投影した男の子の主人公ではなく、女の子の主人公にしたことに理由はありましたか? かっこいい怪人が好きなのは男の子だけではないので、これはとても素敵なアイデアだと思いました。
コスタンスキ監督:僕のなかでは女の子が主人公のほうがピンときたんですよ。ストーリーとしても面白いですしね。自分の実体験にも基づいているんです。僕の周りには強い女性が多くて、自分はどちらかというと(ミミの兄の)ルークのタイプ。脇に押しやられちゃうような感じですね。PG(サイコ・ゴアマン)に対して堂々と立ち向かえる存在として、もとから強さのあるキャラクターが必要だった。そう考えたときに、僕にとっては女の子のほうがしっくり来たんです。
ミミ役のニタはミミそのものなんですよ

――ニタ-ジョゼ・ハンナが演じるミミは強烈なキャラクターでしたね。あの演技はどうやって引き出されたんでしょうか。
コスタンスキ監督:面白いことに、何もしなくてもニタ本人がミミそのものなんですよ。これは本人も認めていました。キャスティングをするときに、自分の中のミミ像に近い人をキャスティングしようと思っていて、そこに彼女がピタリとはまったんです。なのでこっちから演技のリクエストをしなくても、そのままで充分だった。こちらから唯一リクエストしたことは、メリハリをつけることでしょうか。ミミは騒がしくてクレイジーなキャラクターなので、少し考えさせられるような静かなシーンでは、「もう少し落ち着いた演技を」と彼女にお願いしました。そうすることによって、ただ“騒がしい子”で終わってしまうのではなくて、このキャラクターの奥行きを引き出せるかなと思ったんです。
――子役たちは本作で色んな怪人やクリーチャーと共演していますが、どんな反応をしていたんでしょうか。特に脳みそのクリーチャーは可愛いかったですね。
コスタンスキ監督:子供たちはどの怪人にもエキサイトしてくれてたんですが、毎日毎日現場でヘンな怪人たちが登場するので、だんだん慣れてきちゃってましたね(笑)。脳みそのクリーチャーにも喜んでいましたけど、PGのほうがインパクトが強かったみたいですね。ただ、彼らはきちんとプロフェッショナルらしく演じてくれていて、それにはとても感謝しています。大人のコンテンツなので、スプラッターなシーンでは血しぶきを浴びたりすることもあったけど、怖がらずにプロの役者としての仕事に徹してくれた。すごく感心しました。

――サイコ・ゴアマンのデザインはどういうイメージでできたのでしょうか。
コスタンスキ監督:自分の大好きな悪役キャラの要素をかき集めたようなものを作りたい、というのが最初のイメージです。なおかつ、フィギュアとしておもちゃ屋さんに並んでいたときに、10歳の自分が手に取りたくなるようなものにしたかった。フィギュアのサイズになっても目に飛び込んでくるキャッチーさが必要だったんですね。PGの身体のピンクの裂け目は、そういったイメージで加えられたものです。90年代のはじめ頃、エイリアンのアクションフィギュアで、青いメタリック塗装の上にシルバーをのせたものがあってスゴくかっこよかったんですよ。それがピンクの裂け目というアクセントのヒントになりました。その他にも、ヴェノムや『ザ・キープ』のモラサール、「マイクロノーツ」のバロンカーザ、「シルバーホークス」のモン・スターなどが参考になっています。
――たくさんの怪人たちのデザインや制作はどのように行われたのでしょうか。ご自身も携わっていますか?
コスタンスキ監督:非常に低予算の映画だったので、クリーチャーエフェクトにあまりお金をかけらなかったんですね。トロントのマスターエフェクトという会社に依頼して多くのアーティストを起用してもらい、時間を割いてもらったんですが、すべてを任せるわけにもいかなかった。なので自分でもかなりの量を担当していて、寝ずに作業していました。彫刻、型取り、成形、ペイント……延々手作業の繰り返しです。プロデューサーのジェシーにも手伝ってもらわなきゃいけなかったくらい。とにかくみんなで力を合わせて作っていました。もちろん、好きだから自分でもやりたい部分もあったけれど、予算がないから自分でもやらざるを得ない、という両方の理由がありました。

――特殊造形アーティストとして様々な大作にも参加していますが、そういった仕事と自分の映画で特殊造形をやるのとではどんな違いがあるのでしょうか。
コスタンスキ監督:大作映画やテレビに携わるときは、監督がどういう意向でそれを求めていて、どういうふうに現場で使うか、という情報はおりてこないんですよ。なので何が起きても大丈夫なように、必要以上に準備をしておかなければいけない。かなり入り組んだ作業になってしまうんです。自分の作品では、どういうふうに撮影をするかを全部自分でコントロールできますよね。自分の作る特殊造形が撮影現場でどう使われるかを分かった上で作ることができるんです。それがすごく大きいですね。
――コスタンスキ監督の短編に登場したキャラクター“バイオ・コップ”が本作に再登場しており、ファンには嬉しいポイントです。彼の登場にはどんな経緯があったのですか?
コスタンスキ監督:バイオ・コップのオリジンストーリーを描いてみようというアイデアがあったんですね。短編の『Bio-Cop』を撮ってから、色んな人に「バイオ・コップをもっと見たい!」と言われていたんですよ。『サイコ・ゴアマン』の脚本を書いているときに、すでに出てきた登場人物だけで物語が進むなかで、新しいキャラクターを登場させたいなと思った。そこでバイオ・コップを入れてみようと。話の筋を考えても、PGが警察に出くわすというのも自然な流れだし、これを機会にバイオ・コップをスクリーンに登場させることもできるし、ファンも喜んでくれるだろうなと思いました。

“子供には見せられないもの”を見せてもらえるとすごく嬉しかった
――コスタンスキ監督が子供のころに好きだったものが詰め込まれている作品ですが、子供の頃の自分がこの『サイコ・ゴアマン』を観たらどんな反応を示すと思いますか? やはり気に入ってくれるでしょうか?
コスタンスキ監督:まさに子供の自分に観てもらいたいと思って作った映画です。子供のころ好きで追いかけていたもの、ビデオショップの棚で見つけたらエキサイトするようなものを作りたかった。『モータル・コンバット』や「ニンジャ・タートルズ」みたいなね。あと、『ガイバー/ダークヒーロー(Guyver 2)』という映画があって、両親が「子供が観ても面白いだろう」と思って借りてくれたんですが、R指定で全然子供向けじゃなかったんですよ。でも、そういう“子供には見せられないもの”を見せてもらえるとすごく嬉しかった。今回の映画ではそういうものが作れたと思っているので、10歳の自分がすごく気に入るような作品になっていると思います。

――「タートルズ」の名前が出てきましたが、脳みそのクリーチャーのデザインはクランゲのイメージもあるのですか?
コスタンスキ監督:どうだろう? 少し入ってるかもしれませんね。
――SFやコメディもコスタンスキ監督らしい要素ですが、『ザ・ヴォイド 変異世界』のようなホラージャンルの作品も撮られていますよね。ホラーにはどんな思い入れがあるのでしょうか。
コスタンスキ監督:最も好きなジャンルのひとつなんですが、子供のころはすごく怖かったんですよね。でも10代のころに夢中になって、ホラー映画を作る職人的な部分をすごく尊敬するようになりました。実際に自分で映画を作ることになると、毎回毎回ホラーを作りたいという感じではないんですね。ホラーはそれ以外のジャンルとはまったく別物だと思っていて、精神的な部分でも大きく切り替えなければいけないところがあります。特に『ザ・ヴォイド』はダークな作品でしたから、自分の精神面もダークなところに置かなくてはならなかった。なのでしんどい部分もあるんです。僕は「観た人がハッピーになるような楽しい作品を作りたい」という気持ちに傾きがちなのですが、それと同時に、ダークなホラーを作るのも楽しいことなので、間違いなく、またそういった作品を作るでしょうね。
『サイコ・ゴアマン』
7月30日(金)よりシネマート新宿ほか全国順次公開
(C)2020 Crazy Ball Inc.