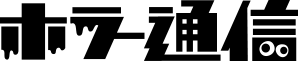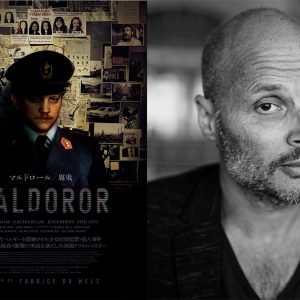この記事は1年以上前に掲載されたものです。

死んだはずの愛する人が帰ってきた。それは奇跡か、悪夢の始まりか。『ぼくのエリ 200歳の少女』原作者ヨン・アイヴィデ・リンドクヴィストの小説を映画化したメランコリック・ホラー『アンデッド/愛しき者の不在』が公開中。本作で長編デビューを飾ったテア・ヴィスタンダル監督にお話を伺った。
舞台はノルウェー、オスロ。突如停電が起きたその日、街は異様な空気に包まれ、そして事態は起こる。本作では、3つの家族の姿を通し、それぞれの“帰ってきた死者との再会”の形と、その先の数奇な運命を描いていく。幼い息子を失ったシングルマザーと同居の父親、同性パートナーを失った老婦人、妻を失った夫と二人の子どもたち……家族の形態も年齢も様々だ。そして、愛する人を失ってからの時間もバラバラに設定されている。

ヴィスタンダル監督「主人公が一人であれば観客もそこに集中して気持ちを沿わせることができると思うんですが、3人の主人公、3つの家族が出てくるので、全員に感情移入できるかというと、それは期待してはいけないところではあります。それでもなおそういう枠組みにしたのは、観客がその登場人物のなかに自分の立場を見つけてほしかったから。別の方法で自分自身を見つめ直すことができるような、誰かを亡くした悲しみについての瞑想のような作品にしたかったのです」
原作小説「Handling the Undead」が発表されたのは2005年。そして、15年前には原作者のリンドクヴィスト自身が書いた脚本が存在していた。本作を映画化する権利を得たヴィスタンダル監督は、自身の手で大幅に脚本を修正し、本作が完成したという。
ヴィスタンダル監督「私が行ったのは、どちらかというと“削ぎ落としていく作業”でした。より大きな舞台で幅広いキャラクターが出てくるようなストーリーだったので、フォーカスを狭めることにしました。もともと二人の老婦人の物語は小説版にはなかった。リンドクヴィストが書いた15年前の脚本には、それが一部の設定として入っていて、私はそれを膨らませることにしました。そうして結果的に3つの家族を追っていく物語になったのです。自分の作品として、瞑想的な詩篇のようなものにしたかったので、そのためにはスケールがある程度小さいものでなければならなかった。親密なものにしたかったからです」

本作の設定を読んで、スティーブン・キング原作の『ペット・セメタリー』を思い起こしたホラー映画ファンは少なくないだろう。ヴィスタンダル監督は、この類似性について「メッセージとしてはすごく近いものがあると思う。原作者のリンドクヴィスト自身がスティーブン・キングの大ファンですから」と答える。
しかし、映画自体が似通ったものかと言えばそうではない。本作ではホラー表現を抑え、『ペット・セメタリー』を観たときに脳裏によぎる疑問を、じっくりと時間をかけて観客に深く突きつける。「自分と愛する人の身にこれが起こったらどうするだろうか」という疑問だ。登場人物たちのセリフは最低限に留められており、静寂の時間と物語の余白が、否応なしに想像を掻き立てる。
ヴィスタンダル監督「セリフは少ない方がいいと思っていました。もともとこの物語はセリフよりも演出で見せたかったし、そもそも人って、身近な人を失った深い悲しみの中ではそんなに多くを話さないんじゃないかと思うんですね。むしろ言葉数が減り、コミュニケーションがうまく取れなくなってしまうのではないか。彼らがそのとき経験していることはそう簡単には言葉で表せないし、それを無理に話させると陳腐になってしまう。我々の存在に関わる実存主義的なすごく大きな出来事と彼らは向き合っているわけで、そこを描くのに、言葉ではやっぱり足りないだろうという気持ちもありました」

“アンデッド”というホラー的な要素を扱いながらも、“死”と対峙する人々のドラマにフォーカスしている本作。しかし、全編に不穏な空気が漂っており、ホラーともドラマとも言い切り難い、独特のバランスが印象的だ。
ヴィスタンダル監督「撮影する前に、私も“これはどのジャンルに落とし込めるんだろう”と自問したんです。だいぶ悩んでから、“メランコリック・ホラー”、あるいは“ホラー前提のドラマ”かな、という結論に落ち着きました。不穏な感じをキープするのは自分にとって大事なことだったんです。脚本を読んだ人たちと話をしたときに、“ホラーじゃないのに、なんでホラーって呼んでるの?”と言われることが結構あったんですよね。でも私は、ホラー映画の不穏さや戦慄、何かが起きそうな感覚ってすごく好きなんです。ただ、ホラー映画はストーリーが盤石でないものも少なくないし、そこで自分のテイストからバランスを見つけていった感じでしょうか」
そんな監督のフェイバリット作品には、黒沢清監督の『CURE』が名を連ねている。
ヴィスタンダル監督「この作品を作った後に観たので、インスピレーションが作品に反映されているわけではないんだけれど、観た瞬間からもう大好きな作品になりました。あのムードやトーン、リアリスティックな部分に惹かれます。多くのホラー映画に比べてホラー表現がすごく抑えられていたから、自分にはよりリアルなものに感じられたし、色んな感情を掻き立てられる作品だったんです。すべての要素に惚れ込んでいるので、おそらく私は黒沢監督の作家性がとても好きなのだと思います」

死と向き合うドラマのリアリズムにこだわった監督は、作品を作るにあたって、グリーフ(死別の悲嘆)に対処する人々のリアクションから、帰ってきた死者のルックスに至るまで、様々な方面から膨大なリサーチを行い、ディテールを作り込んでいったという。
ヴィスタンダル監督「人が誰かを失い、その悲しみと向き合う時、どんなリアクションするのかということもリサーチの中に含まれています。グリーフのセラピストの方に話も聞きましたし、それに関する本も読み込みました。それを経験していない方にとっては、登場人物のリアクションが不自然に感じられるところがあるかもしれないけれど、すごくヒューマンで自然なものになったと思います。
誰か愛する人を失った時というのは、その喪失のせいで脳が機能しなくなったりすることもあるんです。子どもに食事を出すのを忘れてしまったり、一週間シャワーを浴びるのを忘れてしまったりする人もいる。そもそも自分の悲しみや痛みを実感するのって、すぐにではないんですよね。誰かを失ったという現実だけがあり、その喪失を実感するまで時間がかかったりするものなのだと思います」

画像:メイキング写真
ヴィスタンダル監督「アンデッドのルックスに関しても、リアリズムを大事にしたかった。実際の死体の映像なども見ましたし、葬儀屋さんや病理学者の方にもご協力いただいてリサーチをしました。埋葬から何日経っているか?といった部分から考えて作り込んでいきました。
ゾンビではないし、生きてはいないんだけれど、ただの死者でもいけないんです。“人間だった”ということを感じさせるような、そのバランスがとても大事でした。観客が見たときにそれぞれ人間性を少しだけ感じられるようなものでなくてはいけなかった。なぜかというと、家族はこの人をまだ愛しているし、“この人とまだ一緒にいたいんだ”っていうことに説得力を持たせなければいけなかったから。そのバランスがすごく難しかったのですが、SFXデザイナーが素晴らしい腕を発揮してくれて、一緒にひとりひとり考えながらデザインしていきましたね」

そんな監督のこだわりに共鳴したキャストの協力も、本作には不可欠だった。監督が“作品のキーとなるシーン”と呼ぶのが、レナーテ・レインスヴェ演じるシングルマザーのアナが、埋葬したはずの幼い息子と再会するシーンだ。仕事から帰ってきたアナは、部屋で横たわるその息子の姿を発見する。アナの表情からは、単純な喜びではない、複雑な感情が見て取れる。レナーテは自身の要望で、この撮影の瞬間に初めて“死んだ息子”の姿を見たのだという。
ヴィスタンダル監督「あれはレナーテのアイデアだったんです。この撮影で初めてその息子の姿を見たいと。原作もそうだったのですが、自分の中でも母親のリアクションはちょっと距離感のあるものなんじゃないかなと予測していたんです。“これは自分の息子じゃない”、“これはただの肉体なんだ”というような客観的なリアクションですね。とても重要なシーンで、いろんな感情が喚起される可能性があるとは思っていました。最初はドアの外から撮ろうと思っていたんですが、レナーテが「自分でもどんなリアクションになるか分からないから、ぜひアップで撮ってほしい」と言うんです。そこで部屋に一緒に入り、間近で撮ることになりました。作品で使っているのはファーストテイクなんです。なにも計画しないで撮った、すごく生々しいリアクションなんです」
『アンデッド/愛しき者の不在』
ヒューマントラストシネマ渋谷、新宿ピカデリーほかにて公開中